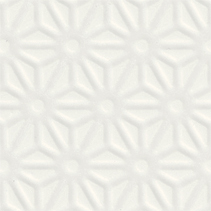「糸屋娘おいと 岩井半四郎」
立命館ARC蔵(arcUP4118)
麻の葉文様とは、麻の葉を象ったとされる文様で、正六角形に縦、横、斜めの直線を引いて構成されています。ただし、麻の葉からこの文様が作られたというよりはむしろ、既存の文様に対して、麻の葉に似ていることからこの名が付けられたと言われています。立命館ARC蔵(arcUP4118)
江戸時代に広まった多色摺版画である錦絵をみてみると、女性の着物の裾や襟元、子供の産着などで麻の葉文様を数多くみつけることができます。とくに子供の産着は、子供の健やかな成長を願って麻の葉文様が使われたとも言われています。一方、女性の着物に描かれる麻の葉文様は、とくに若い女性の着物に描かれることが多く、若い女性向けの文様であったことが現存する錦絵からも伝わります。また、麻の葉文様の人気は、歌舞伎役者の影響もあったと言われています。しかし、江戸時代の生活風俗を記した『守貞謾稿』(天保8年起稿[1837])には「万字繋・麻葉等は不易の紋と云ふべし。」とあり、定番の文様として浸透していたことがわかります。現在も着物はもちろんのこと、インテリアデザインにも使われていて、私たちにとっても身近な文様といえます。
キョーテックコレクションには麻の葉文様が使われている型紙が約18,000枚中220枚ほど確認できます。さまざまにアレンジされていて、文様として親しまれていた様子がうかがえます。そこで、麻の葉文様が使われた型紙をコレクションから紹介していきます。